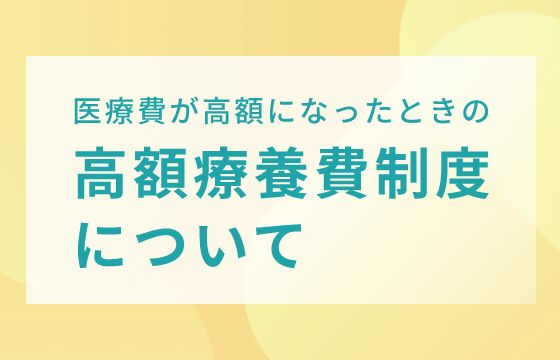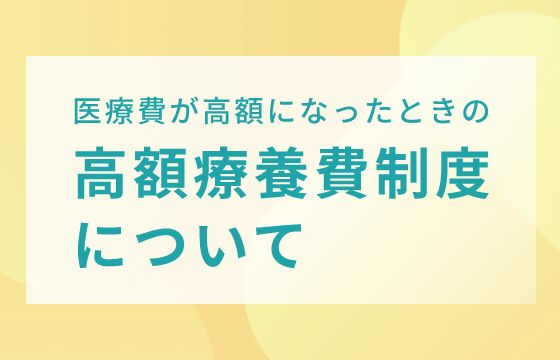

高額療養費制度に関する用語集
- ・オンライン確認資格
- 医療機関や薬局の窓口などで、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等によって、オンライン上で患者の資格情報(診療/薬剤情報など)が確認できる仕組みです。
- ・介護保険(制度)
- 介護を社会全体で支えることを目的に2000年に創設された制度です。40歳以上の国民が介護保険料を納付する義務を負います。介護サービスの利用者は原則1割(所得によっては2〜3割の場合もあり)の自己負担となります。原則、65歳以上で要介護・要支援と認定された際に、介護サービスを利用することができます。
- ・確定申告
- 1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、国(税務署)に申告・納税する手続きのこと。主に個人事業主やフリーランスで所得がある人が対象になります。また、企業に勤めている人も税務署に申告を行うことで、源泉徴収された税金や予定納税額がある場合、過不足分を精算することができます。
- ・合算高額療養費
- 1か所の医療機関等への支払いだけで自己負担限度額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関への支払いを合算して自己負担限度額を超えれば、高額療養費の支給を受けることができます。
なお69歳以下の場合は、医療機関等に支払った同じ月の自己負担額を、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に分け、それぞれで自己負担額が21,000円を超えたもののみ合算することができます。
- ・共済組合
- 主に、公務員(国家公務員、地方公務員)や私立学校の教職員とその家族などが加入する、相互扶助を目的とした公的医療保険制度です。医療保険(短期給付事業)、年金(長期給付事業)、福祉事業を一体的に運営し、組合員が安心して働けるために、生活を支えることを目的としています。共済組合には、大きく分けて国家公務員共済組合と地方公務員共済組合があります。
- ・健康保険(被用者保険)
- 病気やけがによる休業、出産、死亡などによって生じる負担に対し、互いに支え合うことを目的とした、公的医療保険制度の1つです。主に企業や、国や地方公共団体に属して働く方を対象としており、被用者保険とも呼ばれます。健康保険の種類には、大企業で働く方とその家族が加入する「健康保険組合」、中小企業等で働く方とその家族が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、公務員等とその家族が加入する「共済組合」、自営業者や無職の方などが加入する「国民健康保険」があります。なお各健康保険事業を運営する主体者のことを「保険者」といいます。
- ・健康保険組合
- 主に大企業で働く人と、その家族を対象とした健康保険です。
- ・限度額適用認定証
- 医療費が高額になる場合に、窓口での支払い額を自己負担額に応じた限度額にするために、医療機関の窓口に提示する証明書のことです。これを提示することによって、1か月の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
- ・限度額適用・標準負担額認定証
- 住民税非課税世帯の方に交付している「限度額適用認定証」と、入院時の食事代を減額することができる、「標準負担額認定証」が一体になった証明書のことです。これを提示することによって、1か月の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられるほか、入院時には食事代も減額されます。
- ・高額医療・高額介護合算療養費制度
- 医療保険と介護保険のそれぞれでかかった自己負担を合算して、年単位(8月1日〜翌年7月31日)で限度額を超えた場合、申請することで超過分が支給される制度のことです。
- ・高額医療費貸付制度
- 高額療養費として払い戻し予定の約8割を、高額な医療費の支払いに充てるための費用として無利子で貸し付けを行う制度です。貸し付け後の残額は、レセプト審査後に高額療養費として被保険者に支給されます。
詳しくは、「自己負担をさらに軽減する仕組み」をご確認ください。
- ・高額療養費受領委任払制度
- 高額療養費として支給される給付金の受け取りを医療機関に委任し、一部負担金に充てることで医療費の支払いによる負担を軽減することのできる制度です。この制度を利用することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
- ・高額療養費制度
- 1か月(1日から末日まで)に医療機関や調剤薬局の窓口で支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合に、限度額を超えた分の金額が支給される制度です。
- ・後期高齢者医療制度
- 75歳以上の方と65歳から74歳までの方で一定の障害の状態にある方が加入する医療保険で、公的医療保険の1つです。75歳になるとこれまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。
- ・公的医療保険制度
- 病気やけがなどをした時に、医療費の一部を国などの公的機関が負担する制度のことです。日本では「国民皆保険制度」を採用しており、全国民が何かしらの公的医療保険に加入することが義務づけられています。公的医療保険制度には、①被用者保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度の3つがあります。
- ・高齢受給者証(資格確認書)
- 70歳から74歳の方が医療機関を受診する際に、一部負担金の割合を示すための証明書です。2024年12月2日に現行の健康保険証が廃止されマイナ保険証に移行したことを受け、高齢受給者証の発行も一部の例外を除き終了しています。マイナ保険証を保有していない(使用できない)場合に、従来の高齢受給者証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。
- ・国民健康保険
- 他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない方を対象にした公的医療保険です。自営業者、パート・アルバイト従業員で被用者保険に加入していない方、定年退職後で75歳未満の方、無職の方などが加入します。
- ・差額ベッド代
- 入院時に個室や、プライバシーへの配慮等がなされた特別な設備のある病室を利用した場合に、通常の保険診療での入院費に加えて請求される費用のことです。差額ベッド代は医療費ではないため、全額自己負担となり、高額療養費制度の対象にはなりません。
- ・指定難病
- 難病のうち、厚生労働大臣が「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定した疾患を指します。
原因不明で治療法が確立されておらず、長期の療養を要し、かつ患者数が一定水準以下であることなどが要件となっています。指定難病の受給者証が交付されることで、医療費助成などの公的支援の対象となります。
- ・自由診療
- 公的医療保険が適用されない、医療技術やサービスのことを指します。美容整形やインプラント治療などがこれに該当します。費用は全額自己負担となります。
- ・住民税非課税世帯
- 世帯全員が住民税の課税を免除された世帯をいいます。生活保護を受給している、前年の合計所得が一定の所得以下などに該当する場合、住民税は非課税になります。
- ・所得控除
- 納税者の状況に合わせて、所得額から一定の金額を差し引くことができる制度で、課税対象となる「課税所得金額」を軽減するための役割があります。これにより、納める所得税や、住民税の負担が軽くなります。主な所得控除には、すべての納税者に一律に適用される「基礎控除」のほかに、配偶者や扶養家族がいる人に適用される「配偶者控除」、支払った医療費に応じて受けられる「医療費控除」などがあります。
- ・診療報酬点数
- 1つ1つの医療行為ごとに厚生労働大臣が定めた点数のことです。1点=10円として診療費が計算されるルールになっています。
- ・診療報酬明細書(レセプト)
- 診療報酬明細書は、医療機関が保険者(健康保険組合や全国健康保険協会など)に対して、患者の診療費を請求するために作成する明細書です。レセプトとも呼ばれています。具体的には、診療内容(診察、検査、投薬、注射など)や、使用薬剤、給付割合などが記載されます。
- ・世帯合算
- 同じ世帯で、同じ公的医療保険に加入している方が医療機関を受診していた場合、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1か月単位で合算し、自己負担限度額を超えていれば高額療養費の支給を受けることができる仕組みのことです。
- ・全国健康保険協会
- 中小企業等で働く方やその家族が加入する健康保険を運営する公法人で、協会けんぽとも呼ばれています。
- ・先進医療
- 厚生労働大臣が保険診療とすべきか評価する必要があると定めた治療法(評価療法)のことです。効果や安全性を確かめている段階の高度な医療技術のため、実施できる医療機関が限られます。先進医療を受けた場合、診察代や検査代、入院代といった通常の治療に共通する部分は保険が適用されますが、先進医療にかかる費用は全額自己負担となります。
- ・総医療費
- 保険適用となる診療費用の総額(10割)のことです。総医療費は、患者さんの所得区分に応じて一部を自己負担し、残りを加入している公的医療保険が負担する仕組みとなっています。自己負担割合は原則1〜3割で、年齢や所得水準によって区分されます。
年齢に応じた一部負担金の割合については、「高額療養費制度について」をご確認ください。
- ・多数回該当
- 当月を含む直近12か月間のうちに、高額療養費が3回支給されている場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下がり、自己負担をさらに軽減することができる仕組みのことです。
詳しくは、「自己負担をさらに軽減する仕組み」をご確認ください。
- ・難病医療費助成制度
- 国が指定した「指定難病」や「小児慢性特定疾病」などの患者さんに対して、医療費の自己負担を軽減する制度です。なお、医療費の助成を受けるには、難病指定医(当該疾患に関する専門的知識と診療経験があり、都道府県知事または指定都市市長によって指定された臨床調査個人票を作成できる医師)が記載した臨床調査個人票の内容が認定基準を満たしている必要があります。
- ・難病法
- 「難病の患者に対する医療等に関する法律」の略称。国が定めた指定難病患者に対する医療費助成や、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査および研究の推進などについて定めた法律です。
- ・被扶養者
- 健康保険などにおいて、本人(被保険者)の収入によって生計を立てている家族のことです。配偶者や子、孫、父母、祖父母、兄妹姉妹など3親等内の親族が対象です。
- ・被保険者
- 公的医療保険に加入している本人のことです。
- ・標準報酬月額
- 健康保険の被保険者について、一定期間の給与総額(給料、各種手当、賞与など)をその月数で割った額のことです。毎年、4月〜6月の3か月分の給与総額の平均額が標準報酬月額として、9月から翌年8月まで適用されます。
- ・付加給付(一部負担金払戻金)
- 医療費の自己負担額が、組合が定めた一定額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度のことです。組合によっては一部負担金払戻金と呼ぶこともあります。支給は原則自動で行われますが、組合によって条件や上限額、対象範囲が異なります。
- ・マイナ保険証
- 健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。