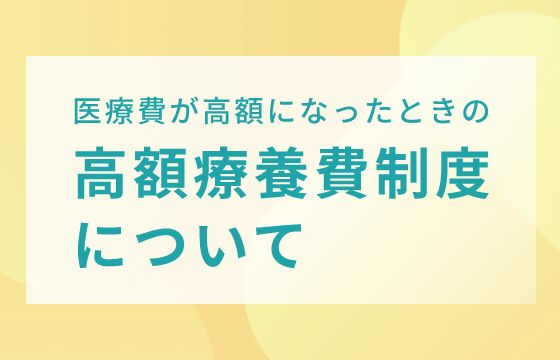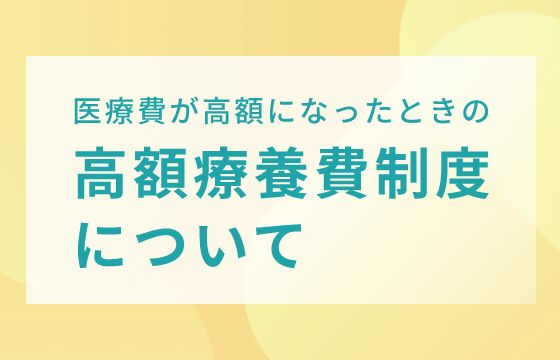

高額療養費制度について、
患者さんが気になる情報を
Q&A方式で紹介します。
- どのような医療費が高額療養費制度の支給対象になりますか?
- 高額療養費制度の対象となる費用は、診察や検査、入院、手術等の保険診療に対して患者さんが支払った自己負担額が対象となります。入院時の「食費」や、個室使用などによる差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは、高額療養費制度の対象にはなりません。
- 自己負担限度額は加入している健康保険によって異なりますか?
- 高額療養費制度の自己負担限度額は、すべての健康保険で共通の基準に基づいて定められています。ただし、加入している健康保険によっては、独自の付加給付を行っている場合もあり、実際の自己負担がさらに軽減されることもあります。詳しくは、健康保険証に記載の窓口や、お住まいの自治体にお問い合わせください。
- 同じ月に複数の医療機関にかかった場合などはどうなりますか?
- 高額療養費制度の申請では、1か所の医療機関等での支払いだけで自己負担限度額を超えていなくても、複数の医療機関等への支払い金額の合計が自己負担限度額を超えていた場合、それらを合算することができます。ただし合算高額療養費のルールとして、69歳以下の場合は、医療機関等に支払った同じ月の自己負担額を、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に分け、それぞれで自己負担額が21,000円を超えたもののみ合算することができます。70歳以上の方の場合、自己負担額に関わらず、それらを合算し請求することができます。
- 病院で同じ月に複数の診療科を受診した場合、それぞれの診療科での自己負担を合計すると自己負担限度額を超えるのですが、高額療養費の請求はできますか?
- 同じ月に複数の診療科を受診した場合、複数の診療科の診療報酬明細書(レセプト)を一本化し、一つの医療機関として合算して申請することができます。医科と歯科、入院と通院別にそれぞれ分けて計算し、①69歳以下の方は、21,000円以上のもの、②70歳以上の方は自己負担額に関わらず、それらを合算し請求することができます。
- 「世帯合算」では家族のどの範囲まで、自己負担を合算できますか?
- 自己負担額の合算は、同じ世帯で、同じ健康保険に加入する家族が対象です。例えば、会社員やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっている場合でも合算することができます。また、健康保険の被保険と後期高齢者医療制度の被保険者が同居している場合、医療保険が異なるため合算の対象にはなりません。
詳しくは、「自己負担をさらに軽減する仕組み」をご確認ください。
- 「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、高額療養費制度とは異なりますか?
- 高額療養費制度とは異なります。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険のそれぞれでかかった自己負担を合算し、年単位(8月1日~翌年7月31日)で限度額を超えた場合に、申請することで超過分の金額が支給される制度です。高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減できるのに対し、高額医療・高額介護合算療養費制度は「年」単位でそれらの負担を軽減することができます。
- 高額療養費の支給申請の期限はいつまでですか?
- 高額療養費の支給を受けるための権利が消滅するのは、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することも可能です。