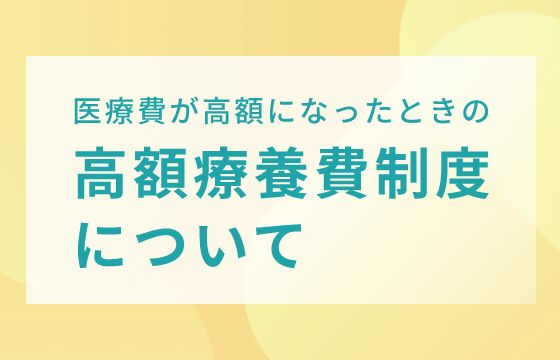窓口で自己負担を軽減するには
「限度額適用認定証」等とは
高額療養費制度では、自己負担限度額を超えた金額が払い戻されるものの、いったんは医療機関の窓口で高額な医療費を支払わなくてはなりません。後日払い戻されるにしても、高額な医療費の支払いは大きな負担になります。そこで、1か月の医療費が高額になることがわかっている場合、事前に加入している健康保険(各自治体、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)に限度額適用認定証、または住民税非課税世帯は限度額適用・標準負担額認定証(以下、「限度額適用認定証」等)を申請し交付を受けておけば、医療機関等の窓口で提示することで、支払い額をはじめから自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行なったマイナンバーカード)を利用することができる医療機関等では、「限度額情報の表示」に同意することで「限度額適用認定証」等を申請しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する際や、健康保険組合等にマイナンバーの登録を行っていない場合は、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」等を保険証とあわせて提示する必要があります。
「限度額適用認定証」等の申請方法については「高額療養費制度の手続き方法」をご参照ください。
「限度額適用認定証」等の適用区分
「限度額適用認定証」等が届いたら、「限度額適用認定証」等に記載されている適用区分の確認を行いましょう。その区分が医療費の自己負担限度額を計算するときの適用区分となります。この区分を判定するための所得は、「限度額適用認定証」等が届いた時点のものではありません。会社員の方などの所得を判定するための標準報酬月額は、毎年4〜6月の3か月間に支給された月額報酬の平均に応じて見直しが行われます。大幅な給与額の変更がない限り、その年の9月1日〜翌年の8月31日までの1年間適用されます。自営業の方の場合は、前年所得により判定した適用区分となり、毎年8月に適用区分が見直されます。
窓口での支払いを自己負担限度額
までにするために必要な各種交付証
70歳以上の方のうち所得区分が現役並みI・Ⅱ(年収約370万円〜約1,160万円)の方は健康保険証、高齢受給者証※、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いになります。また、所得区分が一般(年収156万〜約370万円)、現役並みⅢ(年収約1,160万円〜)の方は、窓口で健康保険証と高齢受給者証を提示することで自動的に自己負担限度額までとなるため、限度額適用認定証は発行されません。なおマイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の申請は不要です(図1)。
【図1】医療機関への交付証

※2024年12月2日に現行の健康保険証が廃止されたことをうけ、高齢受給者証の発行も一部例外を除き終了となりました。今後はマイナ保険証の利用が基本となりますが、マイナ保険証を保持していない方には、高齢受給者証に代わるものとして「資格確認書」が交付されます。
所得による適用区分については「自己負担限度額について」をご参照ください。
「限度額適用認定証」等の有効期限に注意
限度額適用認定証の有効期限は、原則として申請月の初日から最長で1年間(毎年7月末まで)と定められており、年度ごとに更新が必要です。ただし、加入する健康保険によって異なることがあります。
また、被保険者の資格喪失や、適用区分の変更、扶養関係の異動などがあった場合には、たとえ有効期間中であっても「限度額適用認定証」等の再申請や返却が必要になります。継続利用を希望する場合は、手続き期限内に忘れずに更新手続きを行いましょう。
◎ミニコラム:限度額適用認定証があれば、高額療養費の申請は不要?
限度額適用認定証(またはマイナ保険証)があれば、はじめから医療機関等での窓口負担が自己負担限度額までになるため、高額療養費の申請は必要ないと思われる方も多いです。しかし、高額療養費制度には「世帯合算」や「多数回該当」、「合算高額療養費」などの特殊なケースがあり、医療機関ではそのような特殊なケースを把握することができません。そのため、これらに該当する場合は、高額療養費の申請が必要です。