中皮腫をご存じですか
木島 貴志先生
アスベスト(石綿)曝露に起因する疾患として、中皮腫という病名を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。現在の日本ではアスベストの使用が全面禁止されていますが、中皮腫はアスベスト曝露から25~50年の潜伏期間を経て発症するため、2030年頃にピークをむかえ、患者数は年間3,000人に及ぶと予測されています1)。また、患者さんの多くがアスベストを扱う工場があった特定の地域に集中していることも、他のがんとは異なる特徴です。
兵庫医科大学病院は我が国における中皮腫の診療拠点の一つとして、全国で年間840人程度と言われる新規発症者のうち、約100人の方が受診する施設です。がんセンター長・呼吸器内科診療部長として、中皮腫診療の先頭に立って取り組まれている木島先生にお話を伺いました。
1)日本肺癌学会編:肺癌診療ガイドライン 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む 2024年版 第2部 悪性胸膜中皮腫診療ガイドライン:総論(https://www.haigan.gr.jp/publication/guideline/examination/2024/2/0/240200000100.html)2024年12月参照
【取材】2021年9月30日(木) ホテルヒューイット甲子園
第1回では、中皮腫のほとんどは肺を覆う「胸膜」に発症する「胸膜中皮腫」であることを伺いました。第2回では、胸膜中皮腫の診断・治療について伺います。肺がんとはどのような点が違うのでしょうか。
胸膜中皮腫はどのように診断されるのでしょうか?肺がんとの違いは?

X線検査やCT検査で胸水や腫瘤が見つかると、胸膜生検を行います。肺がんは胸水の細胞診で診断できますが、胸膜中皮腫は胸水での診断が難しいため、胸腔鏡下で観察しながら、胸膜に広がった結節(しこり)のような組織を採取します。胸に針を刺して胸水を採取する検査に比べて、胸腔鏡下の生検は皮膚を切開して装置を挿入して行うため、患者さんにとっては侵襲のある検査ですが、確定診断のためには必要です。なぜなら、中皮細胞は胸水中では変形しやすく肺がんとの区別が付きにくくなるため、組織を採取して遺伝子異常を検出できる染色を含む免疫染色によって確かめる必要があります。
また、胸水の検査では、例えば肺がんではCEAという腫瘍マーカーが高値を示すことが多いですが、胸膜中皮腫では陰性を示します。胸膜中皮腫では胸水中のヒアルロン酸が上昇しますが、胸膜中皮腫に特異的なマーカーではないので、やはり組織を採取しないと確定診断が難しいのです。
細胞診での診断は、胸膜中皮腫の診断に熟練した病理医以外では難しい場合が少なくありません。セカンドオピニオンや転院で当院に来られた患者さんの場合は、元の病院で採取された組織を全部取り寄せて、病理医が見直しを行います。
なお、確定診断され申請手続きを行えば、石綿健康被害救済制度の認定を受けられる場合もあります。
外科手術の対象となるのはどのような患者さんですか?
胸膜中皮腫は根治の難しい病気であり、外科的切除の可否についてはまだ意見が分かれている段階ですが、当院では積極的に手術を行っています。リンパ節や他臓器へ転移していない早期の患者さんで、上皮型と診断された場合には手術の適応となります。
胸膜中皮腫は、組織学的には大きく3つの型に分類されます。一部に特殊なものもありますが、大まかには約80%の患者さんが上皮型で、続いて15%が肉腫型、5%が二相型という割合です。上皮型以外の場合は手術をしても再発が多いとされています。
どのような手術を行うのでしょうか?
以前は病変のある片肺と胸膜をすべて切除し、残った切除側の胸郭に放射線を当てる胸膜肺全摘術が主流でした。しかし、片肺になってしまうと在宅酸素療法が必要になるなど、その後の患者さんのQOL(生活の質)に大きく影響します。
現在では胸膜切除/肺剥皮術といって、胸膜を剥いで肺実質を残す方法が主流です。果物のミカンを想像していただくとわかりやすいのですが、ミカンの皮と身を全てとってしまう胸膜肺全摘術に対して、こちらは皮だけを剥いで実を残すというイメージです。
肺実質を残すためには、原則術前・術後化学療法を各3コース行います。かつては胸膜中皮腫の患者さんは手術しても予後が変わらないと言われていましたが、こうした集学的治療*によって予後が改善されるようになりました。
ただし、胸膜を削ぐと術後の癒着などのために肺が硬くなって膨らみが悪くなりますので、もともと肺機能の悪い方では早期の上皮型であっても手術が難しい場合があります。第1回でお話ししたように、アスベスト曝露を原因とする胸膜中皮腫は30~40年を経て発症しますから、患者さんは高齢の方が多くなります。粉じん曝露している上に、さらに喫煙習慣があれば既に肺機能が悪くなっています。そのため、早期発見ができて、なおかつ体力のある全身状態の良い方が手術の対象となります。
*集学的治療:より高い治療効果を目指して、外科的治療、内科的治療、放射線治療など複数の治療法を組み合わせて行う治療法
早期発見の患者さんであれば手術できる可能性が高く、さらに現在では両肺を残す手術ができるということですね。
手術しない患者さんの薬物療法は?
胸膜中皮腫で保険適用が認められている、いわゆる抗がん剤(細胞障害性抗がん剤)は2つの薬剤に限られています。術前・術後化学療法としても、また、手術が難しい場合にも、2種類を組み合わせる併用療法が標準的な治療です。
近年では、手術ができない患者さんにとっては免疫チェックポイント阻害薬*が有力な治療選択肢となっています。
肺がんの薬物療法ではドライバーがん遺伝子**の特定が進み、それらを標的とした分子標的薬を使えるようになって、生存期間が延びました。
胸膜中皮腫ではドライバーがん遺伝子が見つかっていないので、免疫チェックポイント阻害薬に期待するということになります。
*免疫チェックポイント阻害薬:がん細胞が免疫機能にブレーキをかけている部分(免疫チェックポイント)に作用してブレーキがかからないようにする薬剤で、患者さんが本来もっている免疫力でがん細胞を攻撃する。
**ドライバーがん遺伝子:がん細胞の増殖に密接に関与する遺伝子。肺がんにおける代表的なドライバー遺伝子としてEGFR変異遺伝子、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、RET融合遺伝子などが見つかっている。分子標的薬はこれらのドライバーがん遺伝子によってコードされる変異蛋白を標的としており、患者さんのがん細胞にこれらのドライバーがん遺伝子変異があるかどうかを調べて適用する。
薬物療法の副作用について注意することは?
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞によって抑えられていた免疫細胞を再び活性化させることで有効性を発揮しますが、免疫が働き過ぎることによって副作用が現れることがあります。これらの副作用は免疫関連有害事象(irAE)と呼ばれます。多いのは皮疹や下痢で、甲状腺や副腎機能低下、間質性肺炎、Ⅰ型糖尿病や心筋炎なども報告されています。
いずれの薬剤を用いるにしても、薬物療法を始める前にはパンフレットなどで丁寧に説明し、患者さんご自身にも治療日誌をつけていただいています。従来の細胞障害性抗がん剤ならば、例えば骨髄抑制(白血球や血小板の減少など)は約2週間後に現れやすいことがわかっているのですが、irAEはいつどのような症状が現れるかが予測できません。当院では、患者さんが異常を感じた際には、速やかに検査し診断できる体制にしています。
QOLを下げないためにはどのような工夫が必要でしょうか?
疼痛管理、呼吸不全の管理の2つに重点を置き、全身のケアを行います。例えば階段を上るのがつらくなって外出しなくなると、サルコペニア(加齢による筋肉量の減少や身体機能の低下)、フレイル(加齢による心身の虚弱状態)になりやすく、食欲も低下するという悪循環になってしまうからです。酸素吸入や痛み止めを使ってもよいので、動くことを心がけていただきます。
栄養管理も大切です。胸膜中皮腫は炎症性の腫瘍なので血中の炎症反応が上がり、貧血になってアルブミンの低下を来たして栄養状態が悪くなる場合もあります。食欲も低下しがちなので、栄養価の高いものを小分けにして食べるように栄養指導を行ったり、経腸栄養剤を利用したりしています。
また、特に片肺を切除してしまった方は、肺炎を起こすと呼吸不全になりやすいので、まずは感染予防が大切です。昨今は新型コロナウイルスの問題もありますが、手洗い、うがいの励行、マスク着用といった生活習慣の徹底をお願いしています。また、インフルエンザ、新型コロナウイルス両方のワクチン接種も大切です。
高齢の方が片肺となると、安静時は問題がなくても少し動くと血中の酸素濃度が下がってしまうことがあるので、在宅酸素療法が必要になる方もおられます。しかし、胸膜切除/肺剥皮術では在宅酸素療法を必要としないものの、むしろ術後の疼痛が残るという声を多く聞きます。
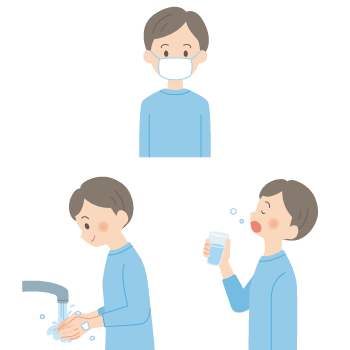
胸膜中皮腫患者さんのほとんどが高齢になってから発症するため、治療が有効でもQOLの維持が難しいこともあります。疼痛管理・呼吸管理に気をつけながら、薬物治療の副作用や栄養管理など全身のケアに注意を払っていくことが重要なのですね。
第3回では、胸膜中皮腫診療における今後の展望についてお話を伺います。
